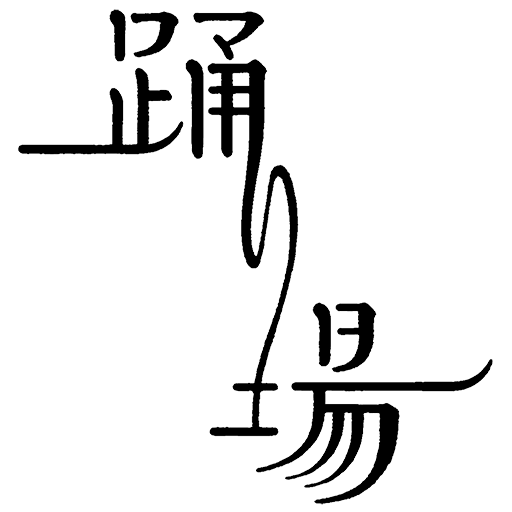広島市立大学日本画科の卒業生・長瀬香織さんより、学生時代から現在の活動についてお話を伺いました。

素材と保存
浅埜 私、膠文化研究会の膠作り体験に姫路に行ってきたんですけど、参加者の1人が先生に「膠の将来はどうなればいいと思いますか?」って訊いていて。その時に「とにかく純度の良いものを作ればいい、ということじゃないと思うんだよね。いろんな膠があるということが重要なんだと思うよ」と言っていて。
多分これは和紙にも同じことが言えるんじゃないかと思った。
保存に適したものだけではなく、その土地で昔から作られてきた素材も含めて幅広く知り、選択し組み合わせて使っていく方が、可能性が広がるんじゃないかと思っている。
作家として保存のことだけ考えていくと表現が狭まっていくことも最近感じていて。揉み紙とか正直あんまり保存の観点から考えると良くないですよね。でも表現という観点からすると、それにしかできない和紙の風合いを活かした表現ができるという…
私は大学院で模写科だったので、それらの選択を迫られるなぁって日本画を学んでいて思っていて。
さらに、その間に漉き手がいなくなったり閉業していってしまうことがあるんですけど。
長瀬 知らないとわからないですもんね。使ってみないと。
大橋 材料をめぐる研究っていうのは僕や長瀬さんが広島にいた頃と比べると、全然状況が変わっちゃってるかも。産業としてどうなっていくのかっていうのもいかんともしがたいところがどうしてもあるんですよね。
「実際どういうものを後世まで残していくのか」と「作ったものをアーカイブして残しておく」っていう事とはやっぱり切り分けて考える必要があると思う。
学問として考えた時は、アーカイブとして状態を保存し、後で見ることができるってことは重要。
同時に長瀬さんがさっき言ったように、昔のものが少しでも残っていれば、それを分析することができるかもしれない。
作家が制作とそれに必要な素材にどういう形で関わっていくのか。